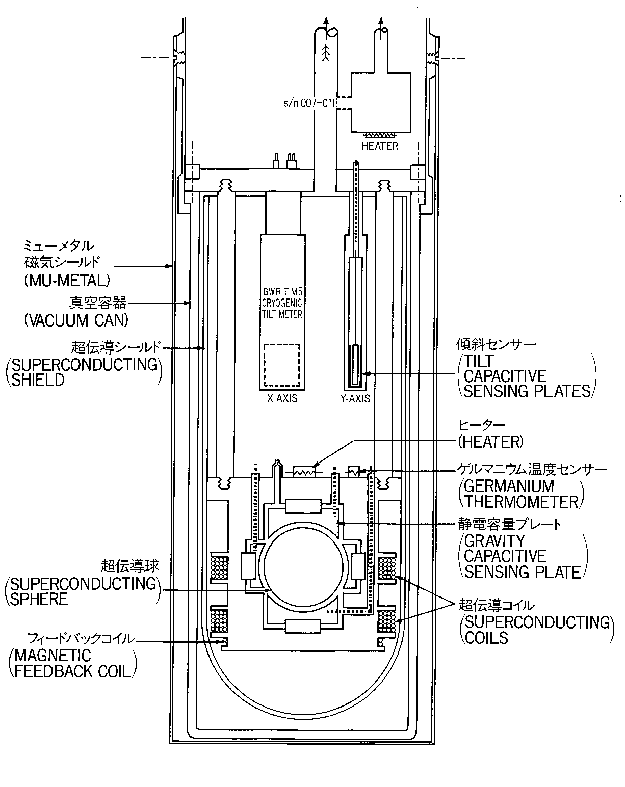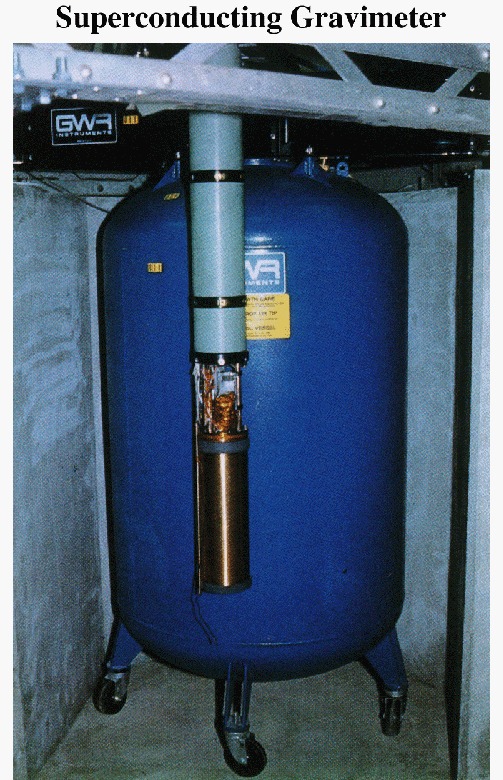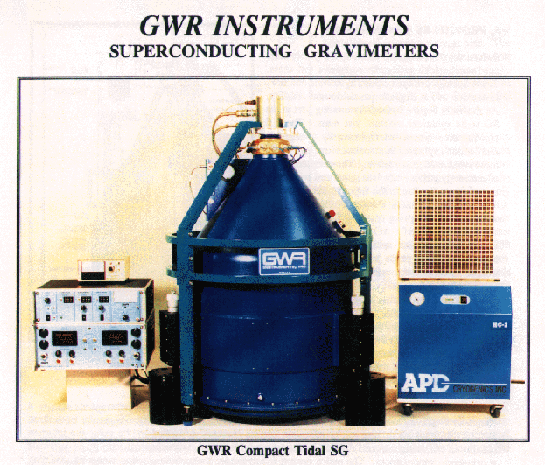超伝導重力計の原理
福 田 洋 一
ふくだよういち
東 敏 博
ひがし としひろ
超伝導重力計は超伝導磁場による磁気浮上力を復元力とする一種の相対重力計であるが,従来のバネ式重力計に比べ,2〜3桁の感度の向上と長期の安定性を得ている.超伝導重力計の基本的な原理と,現在,唯一市販されているGWR社の超伝導重力計の概要について説明する.
1.はじめに
重力測定の方法には,重力の絶対値を測定する絶対重力測定と,重力の時間的な変化や異なる地点での重力の差だけを測定する相対重力測定の2つがある.絶対重力測定は,重力が鉛直方向に働く加速度であるという本来の定義に従い,自由落下する物体の距離と時間を精密に測定する.これは原理は簡単であるが,実際の測定はたいへん難しく,最近,ようやく1μgal(10-8m/s2)の精度での測定が可能になったというのが現状である.また,絶対重力測定の一つの欠点は,原理的に連続観測が不可能なことである.現在,計測の自動化によって,数秒〜10秒に1回程度の繰り返し測定は可能になっているが,この間の実際の計測時間は,落体が落下しているわずか0.1〜0.2秒程度であり,相対重力計での連続測定とは根本的に意味が異なっている.
一方,相対重力測定は,重力の空間的あるいは時間的な変動成分だけを測定するので,絶対測定に比べ測定の大幅な簡略化が可能である.このような目的のため,様々なタイプの重力計が開発されてきたが,それらの多くは一種のバネ計りと考えると理解しやすい.バネ計りが重りの変化をバネの伸びの変化として計るのに対し,重力計はおもりの質量は一定で,重力の変化に伴うおもりの位置変化,すなわち,バネの伸びの変化を測定するものである.
超伝導重力計も原理的にはこのようなバネ式の重力計と同じであるが,バネの反発力のかわりに,超伝導現象の特徴の一つであるマイスナー効果(完全反磁性)による磁気反発力を利用し,重力の変化を永久電流磁場による磁気浮上力とつり合った超伝導体のおもりの位置変化として検出する.このため,超伝導重力計では永久電流による極めて安定な復元力と同時に,極低温状態ではすべて物質が安定になることやセンサーの低雑音化などが相まって,従来のバネ式の重力計に比べ,2〜3桁の感度の向上と,極めて長期的な安定性を獲得している.
小論では,現在,唯一市販されているGWR社の超伝導重力計を例として,超伝導重力計の原理とその基本的な構成について解説する.
2.超伝導重力計の測定原理と構成
図1は超伝導コイルを流れる永久電流が作る磁場内で,超伝導物質で作られた球(実際はニオブ球が用いられており,以下,試験球と呼ぶ)の浮上する様子を示したものである.超伝導状態では,試験球は磁場を浸透させない反磁性体の性質を持ち,球の表面には,コイルの作る磁場を打ち消すような電流が発生し,その反発力によって浮上する.すなわち,この磁気浮上力が従来のバネ式重力計のバネに相当し,重力の変化に伴う試験球の位置変化を検出することで重力の変化を測定することが可能である.実際の超伝導重力計では,測定感度や安定性の向上の為,以下のような工夫がなされている.
図2はGWR社製の超伝導重力計の検出部を示したものである.GWR社製の超伝導重力計は,現在,液体ヘリウムを入れるデュアーや周辺装置の構成の違いで幾つかのタイプが存在するが,心臓部である検出部の基本的構成は同じである.
図2では,図1と異なり,超伝導コイルが2つ用いられていることに気付く.試験球を浮上させるだけであれば,超伝導コイルは下側の1つで十分であるが(実際,超伝導重力計の調整の一段階では下側のコイルだけを用いて試験球を浮上させる),上側のコイルは超伝導重力計を実用的に運用するうえで極めて重要な役割を果たしている.コイルを一つだけを用いた場合には,コイルの作る磁場の勾配が強くなりすぎるため,重力の変化に対する試験球の位置の変化が小さく,重力計の感度が悪くなる.また,磁場の水平成分の上下方向での変化が大きくなるため,重力計の揺れなどに伴う試験球の水平位置の変化で,見かけ上の大きな重力変化が生じる.このような理由で,GWR社製の重力計では超伝導コイルをもう一つ用意し,上下2つのコイルの作る磁場の合成によって試験球周辺の磁場を出来る限り一様にすると共に,両者の強さを調整することで磁場の勾配を弱め,重力計の感度をあげる工夫がなされている.
実際の試験球の位置変化は,図2のように,球の上下と周辺を取り囲む円筒状(図では左右に分かれたように見える)の電極で構成された静電容量ブリッジの容量変化として検出される.ただし,球の位置と静電容量の変化の関係は線形ではなく,さらに磁場の強さも完全には一様でないため,球が中心位置から離れた場合には非線形性の影響が強くあらわれる.このため,検出部の底部に設置されたフィードバックコイルを用いて球が常に最初の検出位置に留まるように負帰還をかけ,その電流量で重力の変化を検出するように設計されている.
検出部には上記以外に,ヒーターとゲルマニウム温度センサー,傾斜センサーなども組み込まれている.次にこれらの役割について簡単に説明しよう.
GWR社の超伝導重力計で用いられているニオブ球は,第一種超伝導と呼ばれる状態にあるが,この状態では試験球は厳密には完全反磁性体とはならず,磁場が表面に少ししみこんだ状態にある.このしみこみの深さが温度に依存するため,温度変化が磁気浮上力の変化を招く.従って,超伝導重力計に要求されている0.1ngal程度の精度を確保するために,検出部の温度変化は数マイクロケルビン以内に抑える必要があり,ヒーターと温度センサーはこのために使用されている.
傾斜センサーは重力計そのものの傾きをモニターするために用いられる.本来,地球の重力はベクトル量なので大きさと方向をもっているが,重力計そのものは1成分の加速度計であり,重力の大きさを正しく計るためには,重力計そのものが重力の方向,すなわち鉛直線の方向に設置されている必要がある.図2の傾斜センサーはこのような重力計の傾きを計測するために用いられ,重力計はこの信号を元に,サーマル・レベラーと呼ばれる装置によって,常に鉛直線の方向に向くように調整されている.
図3は超伝導重力計システム全体の概略図である.
検出部全体は図2のように高真空の容器内に納められ,また,外部磁場の影響を避けるため,容器全体はミューメタルの板で磁気シールドされている.さらに,このセンサー部全体が液体ヘリウムにつかるようにデュアーの中に挿入され,デュア全体が前述のサーマル・レベラーで支えられた構造をしている.
重力計を維持・管理する上で超伝導観測の難しさは,液体ヘリウムでセンサー部を常に極低温に保たなければならないことである.たとえ計測システムに何らかのトラブルが発生し,データが取得出来ないような状態が生じても,センサー部は常に極低温に保っておく必要がある.一旦,この極低温の状態が破れた場合,重力計を再度使用可能な状態にするためには,単に液体ヘリウムを補充するだけにとどまらず,極めて複雑で時間のかかる(室温から重力計が測定可能の状態に復元するためには,通常,最低でも3週間程度の作業時間を要する)手順を踏む必要がある.このため,超伝導重力計では液体ヘリウムの定期的な補充と,そのロスを抑えるための冷凍機の運転管理が極めて重要な作業となっている.また,重力計そのものも液体ヘリウムのロスを抑えるための様々な工夫がされており,たとえば熱伝導を抑えるため,センサー部と外部との接続は必要最低限の信号線で結ばれるように設計されている.試験球の位置の調整などで,超伝導コイルの電流値を変化させなど必要が生じた場合は,その間だけマグネットコイルと呼ばれる専用の接続線を挿入し,調整終了後には不要なケーブル類は,すべて取り外すようになっている.
実際の超伝導重力計は,図3に示すように,デュアーとセンサー部,極低温を保つためのコールドヘッド,冷凍機コンプレッサー,コンプレッサーの水冷用チラー(循環式の水冷却装置),制御部,データ集録装置などが加わり,これらの管理にはかなりのマンパワーが要求されていた.しかし,後述のごとく,最近ではよりメインテナンス・フリーの重力計も作られるようになってきており,このような新しいタイプの重力計が普及すれば,超伝導重力計もより手軽に使えるようなることと期待される.
3.最近の超伝導重力計
米国GWR社によって1980年代後半に初めて市販された重力計はTT−70型と呼ばれるタイプで,我が国が保有する5基(江刺,松代,京都,インドネシアのバンドンおよび昭和基地)を含めて,現在,全世界で十数基が観測を行っている.
TT−70型は,当初,写真1に示すように,架設台に取り付けた水平支持枠によってデュアーを吊り下げる方式(トップマウント)を採用していたが,最近になって,多くの観測点で,下から支える「ボトムマウント」方式に改造が行われている.この変更は,ノイズレベル(特に短周期帯)の軽減に効果があるとされており,京都においても,改造後,短周期帯において,1桁程度のノイズレベルの減少が確認されている.TT−70型は,基本設計として,液体ヘリウムを200L充填できるデュアーを持つため,装置全体としてかなり大型になる.200Lの液体ヘリウムを用いた場合,冷却装置(コールドヘッド・コンプレッサー系)が正常に作動する限り,約1年半の連続観測が可能であるが,冷却装置無しでは,2ヶ月間の連続観測も困難である.
1990年代になって,GWR社ではより容易に設置可能な小型の超伝導重力計の開発を進め,デュアー容量が125Lで,重量約100kgのボトムマウント方式のコンパクトタイプを製作した.現在,GWR社ではこのタイプ(Compact Tidal Gravimeter:CT型)しか製造しておらず,すでに,多くの観測点ではこのタイプが使用されるようになっている.我が国保有の超伝導重力計としては,阿蘇,キャンベラ,名古屋に設置されているのがCT型である.
CT型は,写真2でわかるように,コールドヘッドを支えるサポートフレームが三脚で直接支持されており,大掛かりな架設台を作製する必要がなくなっている.また,デュアーの高さが100 cmとTT−70型(150 cm)に比較して低いため,設置場所(特に観測室の高さ)についての制限が大幅に緩和されている.しかしながら,重力計としては,CT型とTT−70型は同じスペックを持ち,性能的にはほぼ同等である.また,CT型ではTT−70型に比べ液体ヘリウムのロスが抑えられるようになっているが,それでも,1年に1〜2回の液体ヘリウムの補充は不可欠であり,そのためのマンパワーや,作業によるデータの擾乱は避けられない.
これらを踏まえ,GWR社では,次世代の超伝導重力計として,Remote Controlled Tidal Superconducting Gravimeter(RSG)の開発を行っている.RSGはCT型をより小型にしたものであり,最大の特長は,ヘリウムの液化が可能な冷凍機を備えることで,観測時に液体ヘリウムの補充を必要としないことである.これは,従来のAPD製コールドヘッドに替え,ULH(Ultra Long Holdtime)Dewar Refrigeration Systemを備えるためで,液体ヘリウムの気化温度である4.2°K以下の温度を得ることができるKelKool 4.2 GM製コールドヘッド が用いられている.デュアー内で気化したヘリウムガスは,Gifford McMahon型Cyocoolerにより再び液化され,デュアー内部に戻される.このようにして,システムが正常に作動している限り,液体ヘリウムを補充することなく連続観測が可能となる.
RSG型では,液体ヘリウムの供給が困難な場所においても観測が可能であるので,観測点設置場所の選択肢が大きく広がる.また,前述のような作業によるデータの擾乱もなく,マンパワーの大幅な削減が可能となる.さらに,RSG型では,コンピュータ・モデムを介して,重力計センサー,エレクトロニクスおよびデータシステムをリモートコントロールすることができるように設計されているので,複数の観測点を,遠く離れた研究室から容易に監視することができる.機器の調整やデータの取得がリモートで可能となり,従来のように,現地ユーザーに対する特別なトレーニングも必要なくなる.GWR社では,現在,RSG型の開発を精力的に進めており,2000年代の早い時期には,このタイプの重力計が実現するものと思われる.
GWR社では重力計センサー部の改良も進めており,最近の一つの試みとして,試験球を2個内蔵したDual Sphere Superconducting Gravimeter(CT−D型)が作られ,実際に使用されている.従来の超伝導重力計では,稀に,試験球の位置が原因不明のオフセットを起こすことで重力シグナルに跳びがみられ,これが,長期データ解析の一つのネックとなっていた.CT−D型では重力計センサー容器に,2個の試験球と静電容量ブリッジを20 cm離して設置し,各試験球を各超伝導コイルを用いて磁気浮上させる構造がとられている.これは,簡単には2台の重力計を一つのデュアーに組み込んだと考えることができ,両方のセンサーに跳びが生じる可能性は極めて小さいので,両者の重力シグナルの差をとることで跳びの量を正確に見積もることが可能となる.これにより,超伝導重力計データの長期信頼性の向上が期待されている.
4.おわりに
超伝導重力計の原理ならびにその実際について概説した.超伝導重力観測のもっとも困難な点は,何といっても極低温状態の維持である.また,極低温状態での作業については,訓練されたスタッフが必要で,そのためのマンパワーの確保も一つの大きな問題である.これらは直接サイエンスには関わりのないことのようにもみえるが,それなくしては,超伝導重力観測そのものが成立しない.これらのことを考えると,先に述べたRSG型への期待は大変大きい.約10年前に,日本に初めて超伝導重力計が輸入されたときは,まったく新しい質のデータを得ることだけで十分意義があったように思われた.現在,新しいサイエンスを開くためには,もはや一観測点のデータだけで不十分なことは明白である.本特集号のタイトルである超伝導重力計ネットワークの趣旨は,まさにこのことにあり,また,それを実現するのは,実は重力計そのものの操作性の向上のように思われる.
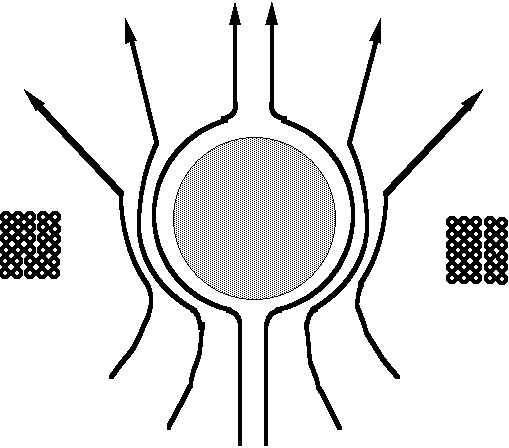 |
図1.超伝導磁場による試験球浮上の概念図
図2.超伝導重力計のセンサーユニット
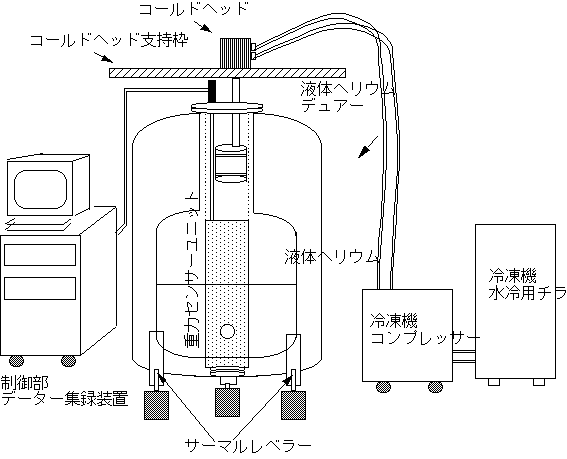 |
図3.超伝導重力計の構成図
写真1.GWR社製TT-70型超伝導重力計.
写真2.GWR社製CT型超伝導重力計.